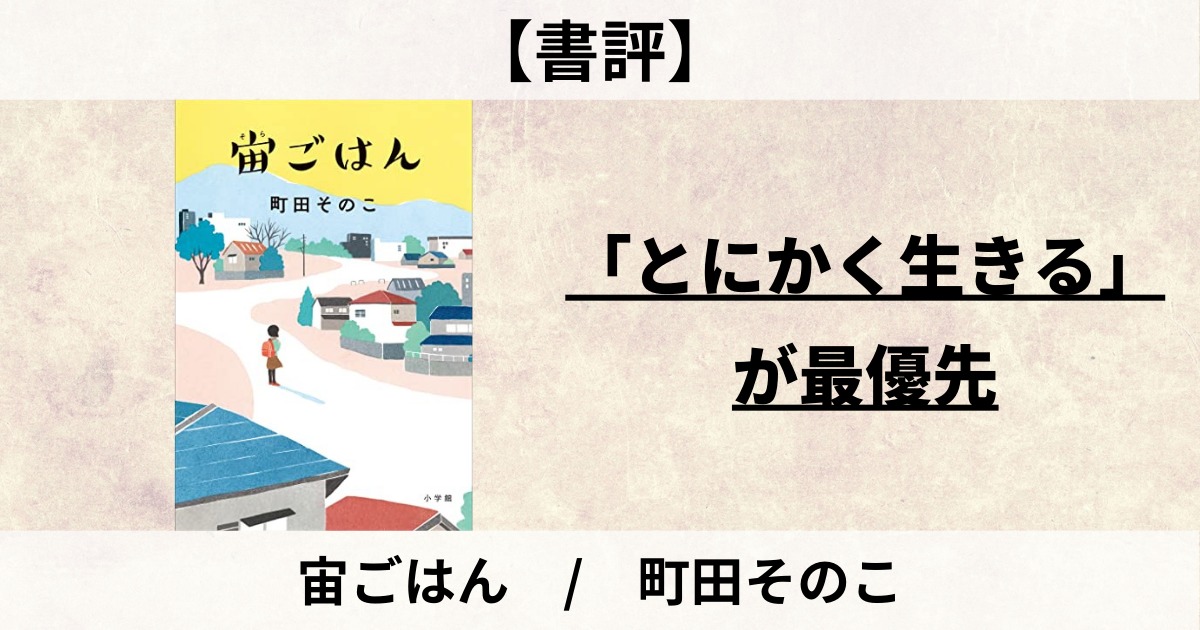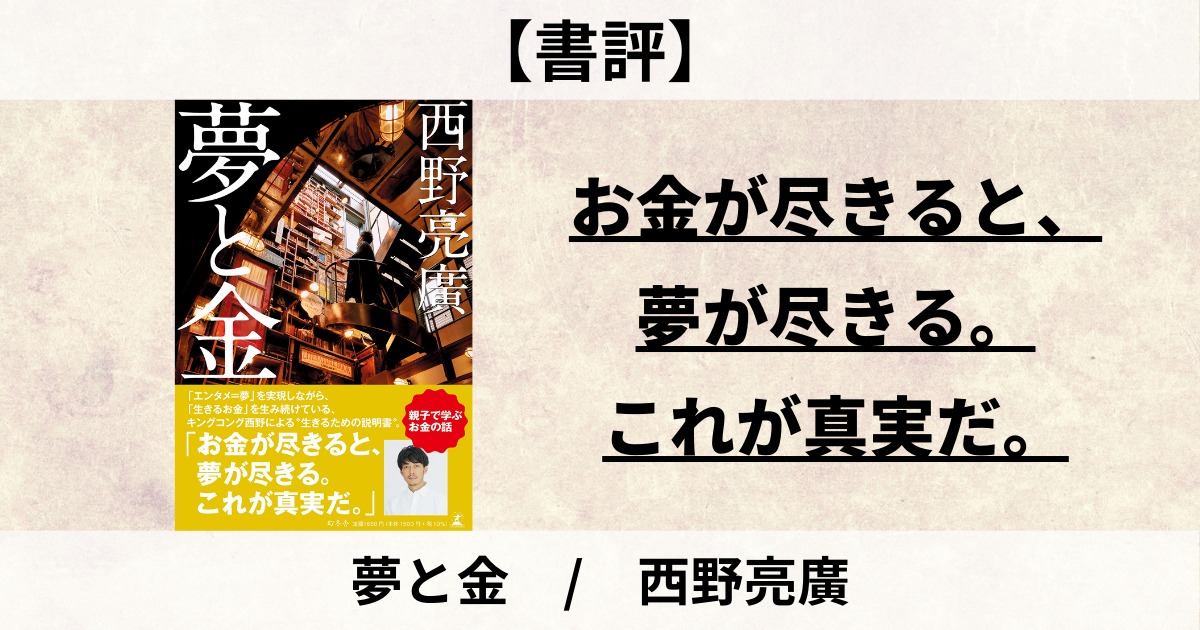こんにちは、みくろです。
今回は、2018年本屋大賞受賞作品、「かがみの孤城」をご紹介いたします。
2004年に本屋大賞が設立されて以来、歴代最高得点を出したのがこの作品だそうです。
いつもならここで感想を書き始めるのですが、今回は我慢…なぜなら、この後ノンストップで書きまくりたいからです。
読後ほやほやの気持ちを、飾ることなく綴っていきます。
- 普通とはなんなのか考えることがある
- 言葉にならない生きづらさを感じている
- 思い切り自分らしく自分の人生を歩んでいきたい
あらすじ
あなたを、助けたい。
学校での居場所をなくし、閉じこもっていたこころの目の前で、ある日突然部屋の鏡が光り始めた。輝く鏡をくぐり抜けた先にあったのは、城のような不思議な建物。そこにはちょうどこころと似た境遇の7人が集められていた――
「Amazon」より
なぜこの7人が、なぜこの場所に。すべてが明らかになるとき、驚きとともに大きな感動に包まれる。
生きづらさを感じているすべての人に贈る物語。一気読み必至の著者最高傑作。
心に響いた言葉
「自分が聞かなくても、誰かが何か聞いてくれるんじゃないかって期待するのはよくないぞ。何か言いたいことがあったら直接言え!」
“雨を好きでも、いいのかもしれない。だけど、学校というところはそんな正直なことを言ってはいけない場所だったのだと、こころは、絶望的に、気づいた”
“これは、質問じゃなくて、本当に聞きたいわけではなくて、私の願望だ。
気づいてほしい、という願望だ。
なのに言えない。そんなに知ってほしいなら口にすればいいと思うのに、それでもなお、言葉は続きが出てこなかった。この先生なら、きっとちゃんと聞いてくれる、と思えるのに。
大人だからだ、と思う。
だから、言えない。
この人たちは大人で、そして正しすぎる。”
「じゃあ、諦めろ。大事かもしれないが、願いを叶えるっていうことにはそれだけのエネルギーがいるということだ。」
“あれはケンカなんかじゃない。
ケンカはもっと、お互いに言葉が通じる者同士がすることだ。もっと、対等なことだ”
「ずっとひとつのことに取り組んできて、これで優勝できなかったり、ピアニストになれなかったらどうしようって、そう思ってるように聞こえたの。それで言うなら、確かに勉強は一番ローリスクなことかもしれない。やればやっただけの結果は出るし、これから何をするにも絶対に無駄にはならないから」
「普通かそうじゃないかなんて、考えることがそもそもおかしい」
感想
ページをめくる手が、あふれる涙が止まらない。
瞬きを、呼吸をする時間すら惜しい。
没入感なんて言葉では表現できないほど、物語が現実を超えてくる。
そんなとんでもない名作に出会ってしまった。
ある日、主人公こころの部屋の中にある鏡が光を放った。その向こうには、オオカミさまと呼ばれる狼の被り物をした少女、そして彼女が管理する大きな城があった。そこには、とある共通の境遇を持つ中学生6人がいた。
…とまぁ、物語冒頭のあらすじはこんな感じ。ミステリー系かなと思っていたのだが、とんでもない。ミステリーは一つの要素にすぎず、ファンタジーであり、ハートフルでもある。何かのジャンルに当てはめることすらもどかしい。もはや「かがみの孤城」というジャンルが成立しているのだ。
「何をもって普通とそうでないかを判断するのか」
そんな答えもないことを勝手に決めつけて、さもそれが当然かのように扱ってしまうのが、人間なのかもしれない。特にまだ若い学生の思考は、ある意味で鋭利な刃物より鋭い。それなりに力を持つ誰かが発信する言葉一つが、全てのルールと常識となり、いじめの火種となるからだ。
大人になった今であれば、社会という大きなコミュニティからみれば、学校がいかに小さくごく限られた時間を過ごす場所であるかということがよくわかる。それは限られているからこそ大事な時間であると同時に、数年もすれば自然と離れていく場所でもある。ただ、だからといってその時間に感じていること全てを軽く見積もるつもりは微塵もない。
「その程度は自分の経験に比べたら…」
「学校なんてほんのわずかな期間に行くだけだから、少し我慢すれば…」
そんな気休めの言葉など、何の慰めにも救いにもならないということを、世のアドバイス好きは頭に叩き込んで欲しい。周りが何をどう伝えるとしたところで、「ほとんどの学生にとっては学校が世界のほぼ全てであり、本人が今感じていることが全ての現実なのだから」。
僕たちは本当の意味で”寄り添う”必要がある。
聞いたって答えてくれないかもしれない。
ノックしても開けてくれないかもしれない。
それでも、傍にいてあげる事。
話したくても話すことができない本人も、きっと同じように辛く、そして闘っている。
ストーリーの求心力とあちこちに張り巡らされた伏線、そして華麗な伏線回収から明らかになる事実と感動のラスト。500ページを超える長編小説を、このレベルの体感スピードで読んだ作品は、後にも先にもありません。
ありがとう、辻村先生。自信を持ってオススメできる作品がまたひとつ増えました。